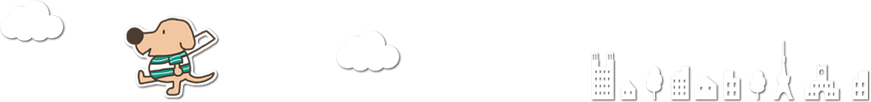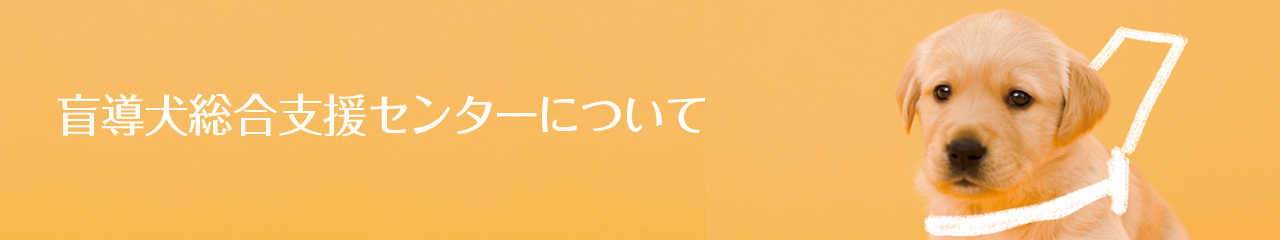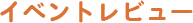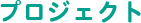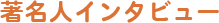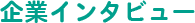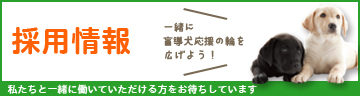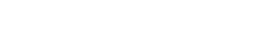現在日本で仕事をする犬というと、
・盲導犬
・聴導犬
・介助犬
・警察犬
・災害救助犬
などが代表的ですね。
それ以外のわんちゃんは、ほとんどがご家庭の家族、愛玩犬として暮らしています。
選りすぐりの血統の中から最適個体が選ばれる

上記のうち「聴導犬」は保護犬を引き取り、育成することもあります。また、警察犬の中での「嘱託警察犬」や「災害救助犬」は、一般の家庭犬を訓練しています。
では、盲導犬や介助犬はというと、健康でそのお仕事に向いている性格を持つ両親から生まれた犬を訓練し、その職業に就くという仕組みをとっています。
盲導犬や介助犬は、温厚な性格で、人のサポートをする作業を楽しんでできる、作業意欲の高い犬が選ばれます。
災害救助犬は、集中力と忍耐力で「探す」というお仕事なので、狩猟本能のある犬たちが選ばれます。
しかし今のように機械化が進んでいない時代は、これら以外の多くの仕事に犬たちが携わっていたのは、犬種の一覧を見ればわかります。
犬の歴史は仕事の歴史
ではそもそも犬はどのように人と暮らしてきたのでしょう。
犬と人、それは仕事の歴史でもあります。
例えばJKCの分類を見てみましょう。
1G:牧羊犬・牧畜犬(家畜の群れを誘導・保護する犬)
2G:使役犬:番犬、警護、作業をする犬
3G:テリア(穴の中に住むキツネなど小型獣用の猟犬)
4G:ダックスフンド(地面の穴に住むアナグマや兎用の猟犬)
5G:原始的な犬・スピッツ(日本犬を含む、スピッツ(尖ったの意)系の犬)
6G:嗅覚ハウンド(大きな吠声と優れた嗅覚で獲物を追う獣猟犬)
7G:ポインター・セター(獲物を探し出し、その位置を静かに示す猟犬)
8G:7グループ以外の鳥猟犬(7グループ以外の鳥猟犬)
9G:愛玩犬(家庭犬、伴侶や愛玩目的の犬)
10G:視覚ハウンド(優れた視覚と走力で獲物を追跡捕獲する犬)https://www.jkc.or.jp/worlddogs/introduction
5Gのスピッツの中には古来人と仕事をしてきた犬種が入っており、また9Gの愛玩犬の中には本来鳥猟犬であったプードルも入ってます。
そしてその他はすべてお仕事犬!
犬種の歴史はまさに「人と犬の仕事の歴史」なのです。
人が求める仕事が犬の性格を作った!
最も古い犬種のひとつと言われる「サルーキ」。
JKCでは「10G:視覚ハウンド」に分類されます。

高貴な風貌が魅力ですが猟犬です。
彼らは中東で遊牧民と共にウサギなどの動物を狩るという仕事をしていました。
そのため非常に動体視力が良く(犬は動体視力に優れています)、スリムな体型で大変速く走ることができます。
逃げる動物たちをどこまでも追いかけるので、走ることと狩猟意欲はものすごいものがあります。
一方でこれらの犬は小さな犬を獲物とみなして本能的に追いかけてしまうようなこともありますので、ドッグラン等では注意が必要です。
ここでは比較的日本で多くみられる犬種を例に取りましょう。
自分で考え狩りをする犬たち

愛らしい風貌だけど、強靭な身体と
高い運動能力を誇ります。
例えば人気の高いミニチュアダックスフントはアナグマを獲るために改良された犬種ですから、強い狩猟欲と体力を持っています。
今とても人気の高いシュナウザーは古くは牧羊犬として仕事をし、その後小型化されてからはネズミや虫などの害獣駆除をするようになったそうです。
害獣駆除といえばミニチュア・ピンシャーもそうです。
害獣、例えばネズミはいつどこに出没するかわかりません。向こうも命懸けで食べ物を取りに来たりするわけですから!
だからこれらの犬たちは飽きることなく一日中動き回っているんですね。
こういった犬種は、人の意思よりも自分の意思で獲物を見つけて捕獲する犬種ですので「自分で判断する」傾向が強いです。
自分で判断する=困った行動になる…?
この「自分で判断する」というのが問題行動というものにつながることがあります。
例えば、テーブルの上のものを食べてしまうという行為があったりします。
「自分で判断する」犬種は人から教わるまでもなく自分でなんでも考えますから、いろんな悪戯をするのが得意!
特に「食べてはいけないものを食べてしまう」など。
どう考えても登れないテーブルの上に登って食べてしまうなんて簡単。
だって彼らは「どうすればあのご馳走が手に入るか」というのを必死に考え、行動するのがとても楽しいからです。
人の指示に従いながら大きな仕事をする犬たち
ボーダーコリーなどの「人の指示に従いつつ非常に体力的にシビアな仕事をする犬たち」がいます。
彼らは人の指示を常に聞きながら、たくさんの動物たちをまとめ上げるという考えられないような高度な仕事をしています。
人からものすごく離れたところからも指示を聞き取り正確に動かなくては仕事になりません。
また、朝、羊等の家畜を出して放牧、夕方帰るまでの間ずっと仕事をしています。
ですので強い精神力と肉体、一日中走り回れる体力、そして頭の回転の速さととびきりの頭脳が必要になります。
普通の環境では持て余してしまう=問題行動につながる
このようにボーダーコリー等の牧羊犬は肉体的にも精神的にも頭脳的にも高度なものを必要とされてきたので、一般のお家で飼われることになるとそのすべてを持て余してしまいます。
結果、必然的にストレスが溜まりそれを発散させるために破壊や吠えなどといった問題行動になることがあります。
羊等の動物を追ってきたので車追いなども代表的な問題行動のひとつです。
もちろんそういうことにならないように穏やかな性格の個体をブリーディングしているので、以前ほど気性の激しい個体も少なくなっていると思いますが、「好きだから」という理由だけでボーダーコリーを迎えて問題行動に手を焼くという方は少なくないと聞きます。
その他の問題行動
これまで説明したように、犬の問題行動にはその多くの場合にその犬種の歴史が関わっています。
例えばビーグルはその狩猟活動の中で、人に獲物の位置を教えるために吠えることを求められてきたため非常に吠えやすいため、ご近所トラブルに繋がったりします。
ドイツ・シェパードは19世紀より警察犬・軍用犬として改良を重ねられてきたので、ハンドラーと仕事には忠実だが外部には警戒するという性質が時に攻撃的な行動に出てしまうこともあります。
「愛犬」と「仕事」を見つめ直してみよう
例えば猟犬であれば、引っ張りっこのような遊びをたくさんしたり、安全な噛むおもちゃを提供してあげたり。
人との追いかけっこ(犬が鬼になり人を追いかけるのがベストです)をお散歩中にやるのもとっても楽しいです!
牧羊犬や使役犬、また鳥猟犬であれば、コマンドごっこを多用して人とのコミュニケーションを増やしたり。
このコラムでは「コマンドごっこ」などの記事も数多く掲載していますのでぜひご覧になってください。
でも本能を刺激する遊びを過剰に行うと、犬たちは必要以上に興奮してしまい問題行動を助長してしまうこともありますので、座れや伏せのような服従訓練(オビディエンス)のような遊びを生活の中に取り入れ、過剰に興奮させすぎないようにしましょう。
競技犬を見るのもヒントになります

人と犬が共通の目標を目指す。それが競技です。
オビディエンスやアジリティといった競技を「人のエゴ」という方もいらっしゃいます。
でも仕事という側面で考えると、オビディエンスは「人の指示に従う仕事」、アジリティは「犬と人が一緒に走りながら擬似の狩りをしている」と考えると、コミュニケーションをとりながら競技をする犬たちが誇らしく見えてくるのではないかと思います。
そう、競技は仕事を失った犬たちが手に入れた新しい仕事、という見方もできます。
「問題行動」の考え方を見直してみよう
そもそも、私たちが「問題行動」と呼んでいるものは基本的に犬にとっては「問題行動」ではありません。
例えばピンポン吠えも、犬たちは「外敵が来たよ!」と教えてくれていることなので、すでにピンポン吠えが定着してしまっている場合は、飼い主さんが「よしわかった、ここからは私に任せろ」という態度に出れば比較的吠えがおさまったという話も聞きます。
ほとんどの飼い主さんが「おとなしく友好的で悪戯をせず吠えもせず、トイレもしっかり覚えてお散歩は楽しく行ってくれるのが良い子」と思っていると思いますが、これは私たちが古来から作ってきた「犬」の姿ではありません。
なんでも理想からズレると「困った!」と考えるのではなく、愛犬の立場、これまで私たちの先人が頑張って作ってきた犬種の歴史に思いを馳せてみると、また愛犬を違った目線で見られるのではないでしょうか。
さいごに〜犬と仕事
犬たちは約1万5千年ぐらい前から家畜化され、人と暮らしてきたと言われています。
冒頭で述べたように犬の歴史は「人との仕事の歴史」でもあります。
そして盲導犬や警察犬などに出会ったときに、今仕事をしている数少ない犬たちなんだな、人と共同作業をしているんだな。
そんな目で見てみると、また犬に対する見方も変わってくるかもしれませんね。

ミニピン×チワワのミックス、シェットランドシープドッグと暮らす。
愛犬とドッグスポーツやディスクの大会に出場し、決勝進出も多数経験。
アクティブな犬との生活を楽しむ。